前記事で次男の今のすがたと成長を振り返ったところで、おうちでのアセスメントを立ててみようと思いました。
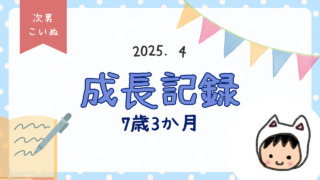
晴れて昨年保育士の資格を取り、発達支援の現場で働きたいなぁと思ったけど、今はわが子のサポートで長時間働くことが難しい。
ってことで今年度は保育の現場から離れて短時間パートに切り替えたので、その分わが子のおうち療育に注力します!
子どもが幸せな人生を送れるようにする。
私も憧れの支援者のような人間になる。
ふたつの夢に向かうためのアセスメントです。
アセスメントとは?
ちなみにアセスメントって何ぞや?
アセスメントの言葉の意味は「評価・査定」。
評価というと「〇〇ができた、できない」のように点数をつけることを想像しがちです。児童発達におけるアセスメントは、子どもの今のすがた(発達段階や特性)を観察し正しくとらえ、どう支援していくかの計画を立てることを指します。支援計画を立てる際には今「何」に困っていて「なぜ」できないのかを探ることが重要になります。
アセスメントの目的は、子どもに点数をつけることではなく子どもの発達段階や特性をしっかり観察して、適切な支援計画を立てること。
次男こいぬのおうちアセスメントシート2025.4
アセスメントにおいて
see(子どもを観察する)plan(そこから得られた情報を元に計画を立てる)do(計画を実行する)
この3つのサイクルを回すことが重要とされます。
なので、ここでは次男の発達段階や特性、課題を箇条書き
考えられる背景をかっこ書きに(see)
それらの情報を元に家で行う手立てを→に記入していきます。(plan)(do)
生活
- 睡眠・起床のリズムがついてきた
(部屋の明かりを消し、家族みんなが布団に入ると自分も素直に入る)
→引き続き、時計のマグネットボードなどを使って見てわかる時間と行動の流れを示していく。家族が手本を見せる。 -
うんちをパンツに出してから「うんちでました」と言葉で伝える
(出そうな時は、力むような表情や動きが止まる様子を見ると周りが分かる。次男が便座に座るのを拒否する。)
→トイレを常に清潔にし、足がぶらぶらしないよう踏み台を使ったり、好きなものの絵をトイレに貼ったり、センサリーツールを使ったりして次男が安心して座れる環境にする。
→まずは便座に座ることを目標にする。座れたら表にシールを貼り、シールがたまったらご褒美をする。 - 散髪・爪切りが苦手
(髪の毛や爪を切ると「痛い」と訴える。ケープをつけるのを嫌がる。寝ている時に切ろうとしてもすぐ起きる。なので髪はお風呂でシャワーを浴びながら、もしくは湯船につかりながら少しずつ切っている。1~2分は静かに切らせている。爪はしっかり体を押さえて、声をかけたり動画を見せながら切っている。)
→感覚過敏が和らぐよう、触覚(識別系)を働かせる感覚遊びを家でも積極的に取り入れる。
→引き続き本人が切りやすい方法で散髪する。様子を見て、少しずつケープがつけられるよう促していく。
運動・感覚
- 箸をグーの手で握って使う
- 部屋の中をうなりながら走り回る
- 寝ころびが多い
(微細な指の使い方が苦手。固有覚・前庭覚の未発達、体幹の弱さ
→体の使い方や体幹を高める動きを繰り返し行う。次男が楽しめるあそびで取り入れる。
認知・行動
- 指示と違うことをわざとする
- ふざけて下半身を出したり、下ネタを言ったりする
(反応を得ようとしている)
→反応を見ている時は、反応せず淡々と促す。関わりややりとりの手段を広げる
言語・コミュニケーション
- 自分の思いと反する時やうまくいかない時に、飛び出し・物を投げる行為がある
(気持ちのコントロールが苦手、もやもやした感情を言葉で表すことが苦手)
→抱きしめて落ち着く時はしっかり抱きしめる。適切なクールダウンの方法を伝えたり、一緒に探したりする。「悔しい」「〇〇がしたかった」などの気持ちを汲み取り代弁する。ルールのあるあそびや勝ち負けのあるあそびの中で、気持ちの調整をしたり、相手を意識した言葉ややりとりの手段を増やす。 - 「今日学校で何した?」などの問いにうまく答えられない
(語彙力が少ない、朝・昼・夜・昨日・今日・今週・来週などの時間の流れをつかめていない)
→家でも絵本を読む機会や会話を増やす
人間関係・社会性
- 自分のペースで動くことが多い
(大人の促しがあれば気づくことが増えている。放デイや学校では友達や先生と楽しく仲良く過ごせている)
→「今から何するんだった?」などの声掛けで促していく。放デイや療育を続けて活用し、専門的な支援を受けたり、社会参加の機会を設ける。自己肯定感を絶やさない。
上記のアセスメントシートはプリプリパレット2025年4.5月号を参考にしてます。
ここで立てた計画がうまくいってるかどうか、モニタリングを半年後くらいにしたいと思います。
忘れないように、がんばれ私。

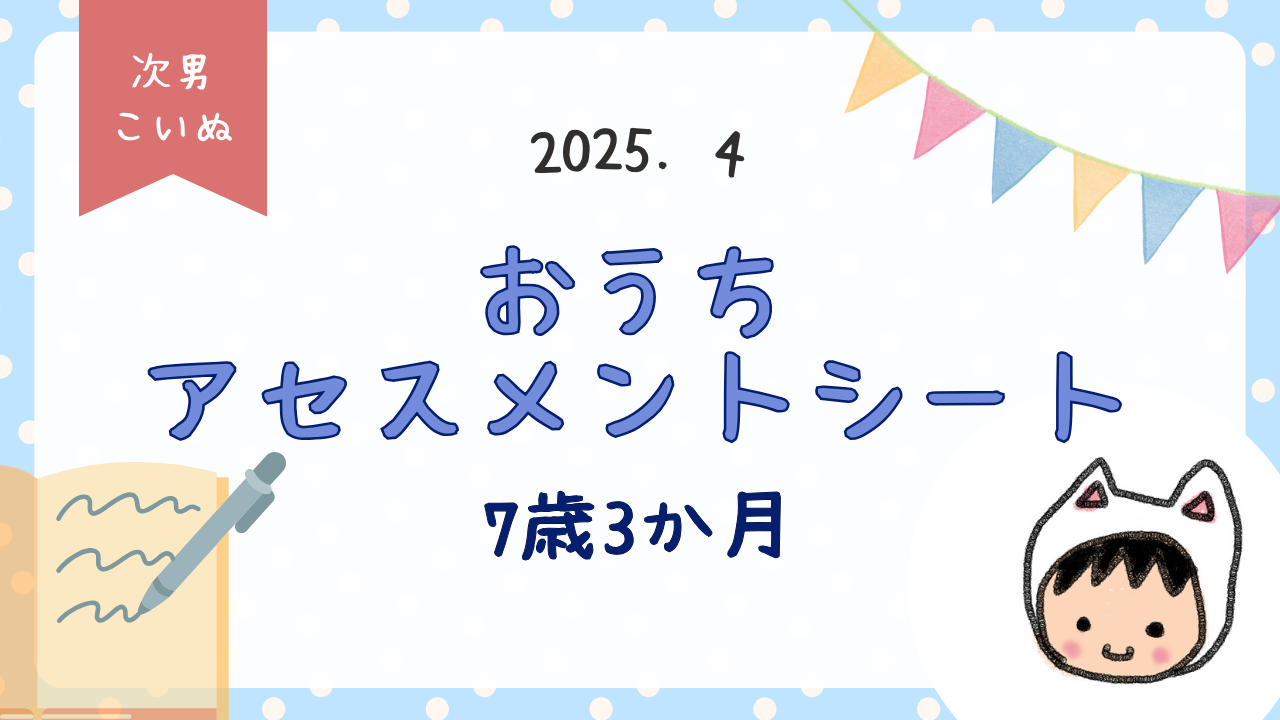

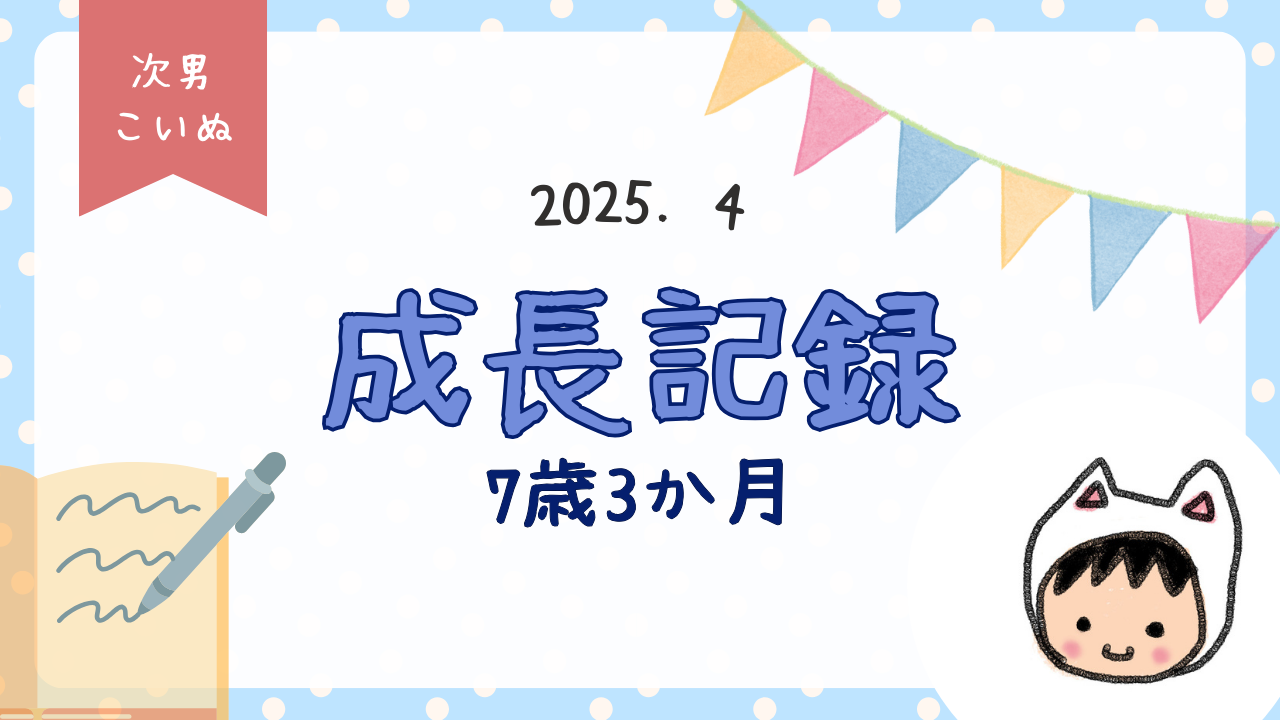
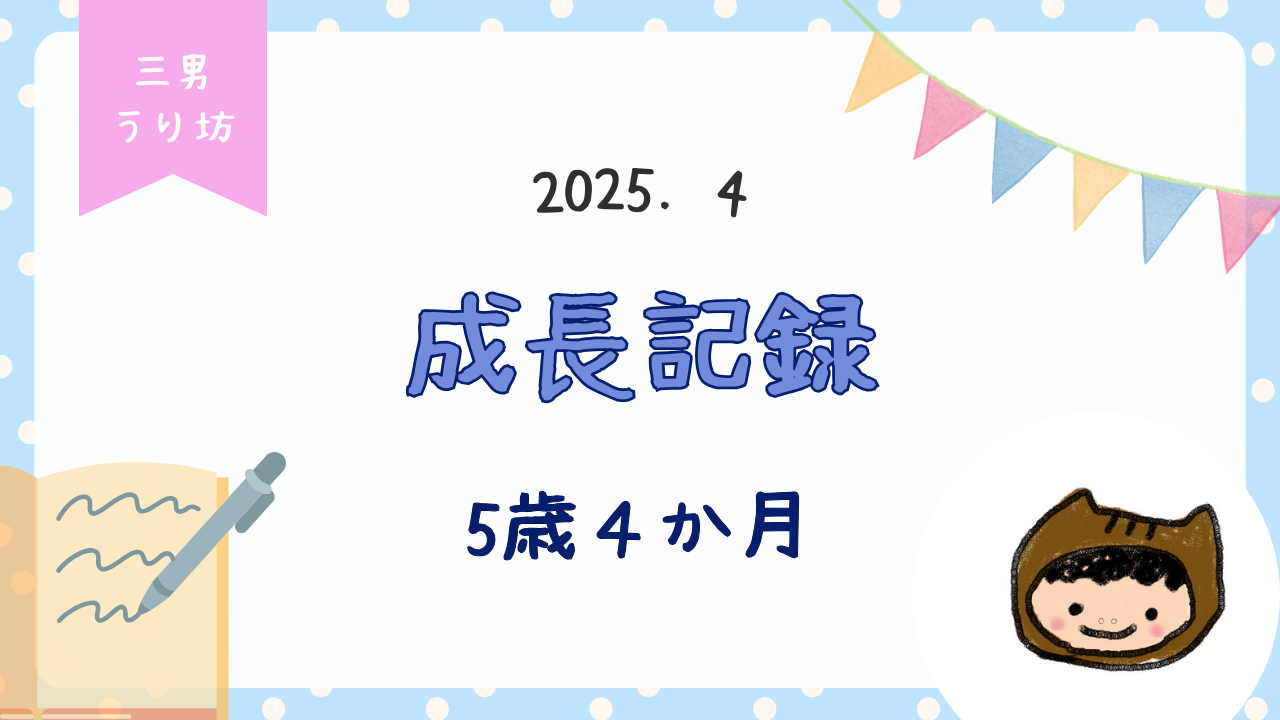
コメント